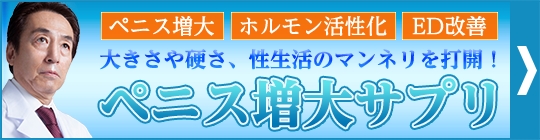公衆トイレで熊親父に口淫される
私は田舎の小さな町で育った。
若いゲイが 発散する機会は皆無に等しかった。
インターネットやアプリが簡単に使えるようになるずっと以前の、60年代後半から70年代にかけて私は、「ホモ」という言葉すら知らずに育った。
その時代は「オカマ」とか「おとこおんな」「かまちゃん」と呼ばれていたと思う。
男を知らない私が欲求不満を解消するには、より多くの創造性を必要とした。
当時の田舎町では、ゲイの男性は社会規範から離れた場所で、愛情や満足感を求めることを余儀なくされていた。
今の人からするとクレイジーに聞こえるかもしれないが、ゲイバーに行くのでさえ、信頼できる会員の紹介が必要だった。
私は18歳で運転免許を取った。初めて車を買ったのは20歳のときだった。
その頃には、自分では認めたくなくても、他の男性と「やりたい」という衝動が私の股間を熱くし、思考を混乱させた。
しかし、新たに手に入れた自由によって、私は同じ趣味を持ち、欲情している男性を探すことができるようになった。
当時、欲求不満を解消するのに一番簡単にチンコを拝める場所は、銭湯や温泉、公衆トイレだった。
まったくの偶然から、私はそのようなトイレがあることを発見した。
それは、町外れにある小さな森林公園の裏手にあった。
そこには、駐車場の端からさらに奥に小道を行くと、コンクリートで出来た小屋に2つの入り口があった。
小屋の上には「トイレ」と書かれた木の看板があり、窓はなく中の様子は見えないようになっていた。
そこに入るためには、車を降りて少し歩かなければならなかった。
森林公園の建物の横を通っていくのだが、建物の陰になっていてほとんど人が通ることはなかった。
また、建物の裏側にも別の駐車場があり、そちら側は昼間でも木々が多い茂って薄暗かった。
そんな場所にあるため、めったに使われることはなく、森林公園の建物にもトイレがあったので裏のトイレの存在を知ったときには、ずいぶん驚いたものだ。
その施設の匂いもはっきりと覚えている。 古い公衆トイレを利用したことのある男なら誰でもその匂いをよく知っているはずだ。
アンモニア臭と汗臭さ小便の匂いが入り混じったような独特の臭いだ。
どんなに手入れが行き届き清潔なトイレであってもこの臭いは空気中に残るのものだ。
そして、その場所は私のお気に入りの場所になった。
個室に入ると、ドアの小さな隙間から覗くことができた。
私は駐車場で獲物が来ないか車の中で待っていた。
親父が運転するシルバーのバンが入ってきた。
私はすぐに男子トイレに向かい個室に入った。
足音が近づいてくるのが聞こえた。
顔はよく見えなかったが袖をまくった毛深い腕に紺の作業着に、汚れた紺のズボン、そして工事用の革靴。
親父はゲイらしさのかけらもない男らしさの典型だった。
私たちの間には仕切りがあるだけだった。
チャックを下ろす聞き慣れた音がした。そして静寂が訪れた。
トイレの壁には鉛筆大の覗き穴もいくつかある。
見知らぬ男が勢いよく小便をする音が聞こえた。
小さな穴から覗き込むと、今までに見たこともない大きさで柔らかそうなチンコが見えた、
そのチンコが黄色い金色の小便を勢いよく放出しているのを見た。
その流れは終わりがないように思えた。
少なくとも1分以上はかかっただろう。
私は畏敬の念を抱きながら、親父が膨張した膀胱を解放するのを黙って見ていた。
最後の数回の放出の後、親父はぐったりとしたチンコを手に持ち、ただそこに立っていた。
親父の素晴らしい亀頭の先っぽには、大粒の小便が光っていた。
私は、親父がチャックを閉めて立ち去るだろうと思っていた。
私は親父の行動を読み違えたのかもしれない。
親父が太い竿をゆっくりと引っ張り、最後の数滴の残汁を絞り出すために先端をしごいてる様子を見続けた。
驚いたことに、親父は止めるどころかズル剥けの太魔羅を扱き続けたのだ。
どうやら私が覗いてるのに気づいているようだった。
親父は見せびらかすように私のほうを少し向き、巨大なバケモノを撫で回した。
私は静かにそれを見ていた。
ズル剥けで雁の張った亀頭はこれまで見た中で最大だった。
大袈裟かも知れないが、使い込んだ親父のズル剥け黒魔羅の標本だった。
おそらく長さは19センチ以上、太さはコーヒ缶ほどだろう。
レモンの半分ほどもある親父の巨大な亀頭が私を魅了した。
私の口は、亀頭をしゃぶるのに十分な大きさなのだろうか?
とてつもなくムラムラと好奇心をそそられ、この機会を逃すわけにはいかなかった。
心臓がドキドキしながら覗き込んだ。
他に誰か来ないだろうか?
親父以外誰もいない! 経験上、次の行動をすぐに決めなければならないことはわかっていた。
親父が車の音を聞いたり、私に嫌気づいたりしたら、チャンスはすぐに終わってしまう。
私はドアのロックを音をたてて戻した。 彼は気づいただろうか?
親父は何をするのだろう? 私は息をするのもやっとだった。
耳をつんざくような静けさの中で、親父が体を動かし、2、3歩歩くのを聞いた。
私は座りしゃぶる体勢で待っていた。
ドアが全開になり、親父が中に入った。
私は気絶しそうになるほどバクバクしてた、岩のように硬くなったチンコが私の興奮を物語っていた。
親父はドアを閉めた。 もう逃げられない。
わずか数センチで向かい合い、親父の巨根が作業着から出ていた。
親父の巨大な勃起したチンコが、私の顔の真正面に向けられた。
まるで突進してくる機関車を真正面から見つめているかのようだった……
私は顔を上げた。
私の喉を使おうとしていた。 鏡のようなサングラスに、引き締まった顎のライン、短い髭に濃いサングラス。
親父が手を伸ばしてサングラスを外した瞬間、またもや倒れそうになるくらいドキドキする瞬間が訪れた。
part 2
隣町に住んでる私の友達の父親だった。
彼らが新しい家を建てて町の反対側に引っ越して以来、私は父親に会っていなかった。
7歳くらいのとき、町の反対側に引っ越したのだ。
この18年間で私も明らかに変わり 彼は少し老けて、白髪が増えていた。
紛れもなく友達の父親だった。
私は心臓の発作を抑えながら、気持ちを整理した。
知らないふりをすればいいのか。 急に計画を変更すれば、彼は私を意識するようになるだろ。
私の正体がばれてしまうかもしれない。
下を向いて彼の視線をできるだけ避けた。私は彼の股間に近づけば近づくほどいいと思った。
それで私は彼に近づくように合図した。 ためらうことなく、彼は一歩私のほうに歩み寄った。
作業ズボンの一番上のボタンを外しながら、私のほうに一歩踏み出した。
そのとき彼の巨根と、刈り込まれていない茂みが目に飛び込んできた。
チンコの臭いが私の鼻を直撃した。
それからの数分間は、私は本能と葛藤し、ぼんやりとしたものだった。
しかし、彼の熟した男根のじめじめとした濃い匂いと、彼の不機嫌そうな声で目が覚めた。
亀頭が私の唇に届くと、彼は言った。
「臭うかもしれんがしゃぶってくれるか?」
私は大きく口を開き彼の洗っていない巨根の塩辛い味を口に含んだ。
これが穏やかな物でないことはすぐにわかった。
彼は私の後頭部に手を伸ばし、いきなり私の喉奥に突っ込もうとしていた。
私は彼の金玉を掴みどうにかして、深い突きを止めることができた。
私は頭を少し戻し喉と顎の力を抜くように努めた。
彼の巨根は匂いと同じくらいおいしかった。
彼が腰を突き上げるたびに、私は喉の力を抜き、より多くのものを受け入れることができた。
彼の大きな亀頭は私の口の中を完全に満たした。
彼はすでに、先走りで漏れていた。
先走りが私の喉の奥を潤してくれた。
私のすべての不安は、純粋な欲望へと消えていった。
実の父親ほどの年齢の男が、私の口を悦ばせたのだ。
欲望と化した動物的本能と、この素晴らしい巨根の持ち主を知っているという優越感は私を鼓舞した。
私は舌を使い、より刺激的に彼の亀頭を刺激した。
すると、彼はますます先走りを漏らした。
彼の巨根は、私の全身の神経を疼かせた。
彼の巨根を永遠にしゃぶり続けることもできたが、残念ながら、彼の性欲は別の計画を立てていた。
彼は私を押し倒そうとしたが、私は必死に抵抗した。
彼は私を壁に押し付け、無理やり喉奥に突っ込んだ。
彼の勃起した巨根が私の喉の奥まで入ってきた。
酸素不足と彼の巨根の強烈な匂いで、私は窒息寸前だったが、彼の太魔羅をくわえたまま離さなかった。
私の頭は彼の太ももに押し付けられ、両手は太ももを掴んでいた。
彼は激しく腰を振り始めた。
亀頭が私の喉を擦り上げ、私の胃は押し上げられた。
何度も嗚咽した、それでも彼の太魔羅をしゃぶることをやめなかった。
喉から食道にかけて、灼けるような痛みが走った。
私の喉の粘膜が傷ついたに違いない。
彼は私の頭を前後に動かし、私の喉を犯すのを楽しんだ。
そして、私の口の中で射精し3、4発床にぶちまけた。
私の限られた経験では、出したらどちらかが直ぐに立ち去るのだが親父の足はその場に留まり、私の喉への攻撃は続いた。
私は両手で彼の腰を押し返し、息を整えようとした。
「オカマ野郎、まだ終わってないぞ!」と言いながら、私の頭を彼の股間に強く引き寄せ、彼は突きのスピードを上げた。
涙が頬を伝った! 喉の奥まで侵入されるたびに、私は息をするのに必死だった。
彼が私の正体を知っていようといまいと、この時点で彼が気にしていないのは明らかだった。
彼は気にも留めず、ただひとつのことを私に求めていた。
私の喉は彼の巨大なイチモツに反発した。 このような暴力的な性的支配を経験したことはなかった。
私はそれが好きになり今まで経験した事がない興奮だった。
私の喉は本能的に大量の唾液を分泌し始めた。
よだれが顎から転がり落ち、私はまるで目の前のご馳走を見てる犬のように感じた。
彼は臭いペニスで私の喉を犯し続けた。
永遠にも思えたが、おそらく5~6分だっただろう。
彼は両手で私の頭を掴み喉の奥まで巨根を押し込んだ。
彼のイカ臭い茂みに埋もれた。 大きな金玉が私のあごを叩き、私は喉が熱くなるのを感じた。
味わい深く、塩辛い唾液が私の口の中を覆った。
疲れ果てた彼は巨根で私の顔の横を叩き、こう言った。
「美味しかったかホモ野郎!」
「ありがとう」の一言もなく精液の跡を残しながら柔らかくなった巨根をパンツに詰め込み、手を洗うこともせずにそのまま出て行った。
私は呆然と座り込み、冷静さを取り戻そうとした。
頬を紅潮させた。 個室には小便と精液の匂いが残っていた。
彼が車で出ていく音が聞こえた。
エンジンの音がゆっくりと消えていった。
そしてそれは終わった。
あれから30年、田舎町でゲイであることが許されなかった時代の青春と性の目覚めを、私はこう振り返る。
田舎町でゲイであることは、まだ影に隠れた存在だった。
友達の父親が、どっちなのか私が知ることはなかった。
彼は私を何者であるかを理解してたのだろうか?どうだろうね?
彼は自分の秘密が私と一緒なら安全だと知っていたと思う。
残念なことに、そのようなことは二度となかったが、私は親友の父親との淫らなトイレでの関係を決して忘れないだろう。
そして、この小さな町でゲイであることを隠さなければならなかったことの苦しみとともに。
終わり